

 創始者と伝えられる華屋与兵衛の曽孫にあたる小泉清三郎らの記録によれば、「握るすし」というのは与兵衛以前にもありました。
創始者と伝えられる華屋与兵衛の曽孫にあたる小泉清三郎らの記録によれば、「握るすし」というのは与兵衛以前にもありました。
しかしそれは、小さく握った飯の上に魚を貼り付け、箱の中で笹の葉の仕切りはしてありましたが、要は、箱ずしのことを指します。この手間と押し付けることで、魚の脂分が抜け出てしまうのをきらった与兵衛が考えついたのが、現代われわれが考えるような握りずしだったのです。
また当時は、「握り早漬け」と呼んだと言われております。


 白えび
白えび、ほたるいか、岩牡蠣、赤いか、真たこ、真鯛、げんげ
白えび
白えび、ほたるいか、岩牡蠣、赤いか、真たこ、真鯛、げんげ
 本まぐろ
本まぐろ、あま鯛、とらふぐ
本まぐろ
本まぐろ、あま鯛、とらふぐ
 さより
紅ずわい蟹、さより
さより
紅ずわい蟹、さより
 本ずわい蟹
本ずわい蟹、なまこ
本ずわい蟹
本ずわい蟹、なまこ
 寒ぶり
寒ぶり、甘海老、槍いか、さより、かさご、あんこう
寒ぶり
寒ぶり、甘海老、槍いか、さより、かさご、あんこう


 鮨は、「江戸前の時代から手掴みで食べるものと相場が決まっている」とよく言われます。しかしその一方で、箸でつまんで食べる人も居るわけです。これはどちらが正しいのでしょうか?その答えは「その人にとって食べやすいのであればどちらも正しい」のです。
鮨は、「江戸前の時代から手掴みで食べるものと相場が決まっている」とよく言われます。しかしその一方で、箸でつまんで食べる人も居るわけです。これはどちらが正しいのでしょうか?その答えは「その人にとって食べやすいのであればどちらも正しい」のです。
しかし、箸でつまむと崩れてしまったり手で掴むと手の温度が移ってしまったりと、一長一短です。結局のところ、手も箸も「綺麗に寿司を食べるためにある」のです。箸でつまむ時は優しくネタとシャリの両方から挟むようにしましょう。また、寿司をひっくり返すようにしてネタを下にして人差し指と中指で支え、舌の上にネタが来るように口に運ぶのが正しい食べ方といわれています。この掴み方は、醤油に漬けるときシャリを崩さないので見た目にも美しく食べることが出来るのです。

 俗に、「寿司を食う時は白身に始まって味の濃いネタで終わる」と言われています。これには味の淡白な白身魚は、トロやアナゴなどの味の濃いネタを食べた後では充分に味わうことが出来ないからだという理由があります。
俗に、「寿司を食う時は白身に始まって味の濃いネタで終わる」と言われています。これには味の淡白な白身魚は、トロやアナゴなどの味の濃いネタを食べた後では充分に味わうことが出来ないからだという理由があります。
しかし、白身魚やヒカリモノなどが好きではない人も、この順番に従わなければならないのでしょうか? 答えは「No」です。寿司は食べたい順番で食べて構わないのです。ただ、先に食べたネタの味が舌の上に残っていると、淡白な味わいがぼやけてしまうのは確かです。こうした場合、次のネタを食べる前にガリかお茶で舌をリフレッシュさせるのが、ネタの食材や握ってくれた職人さんへの礼儀なのです。

 寿司のネタの中には、その儚い味と香りを楽しむものがあります。俗に、『旬のアナゴは木の芽の香りがする』と言われています。このように、ネタの味わいの中には香りも含まれているのです。
寿司のネタの中には、その儚い味と香りを楽しむものがあります。俗に、『旬のアナゴは木の芽の香りがする』と言われています。このように、ネタの味わいの中には香りも含まれているのです。
しかし、匂いの強い香水を振りまいてきたり、周りに構わず喫煙を始めたりするお客も中には居るわけです。マナーと言うものは、『自分さえよければそれでいい』という考え方の対義語です。周りのお客さんに迷惑を掛けてしまうのではないかと思ったら、即座にやめる勇気も必要なのです。


みなさんご存知の通り、新鮮な魚の栄養がたっぷりの寿司は、日本の食文化にはかかせません。
また、 調理に油を使わないのでとってもヘルシーです。


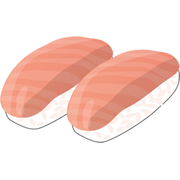 まぐろ(大とろ)
70.3kcal
まぐろ(大とろ)
70.3kcal
 まぐろ(中とろ)
57.1kcal
まぐろ(中とろ)
57.1kcal
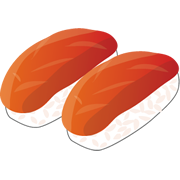 まぐろ(赤身)
44.9kcal
まぐろ(赤身)
44.9kcal
 いか
38.7kcal
いか
38.7kcal
 サーモン
51kcal
サーモン
51kcal
 ほたて貝
44.7kcal
ほたて貝
44.7kcal
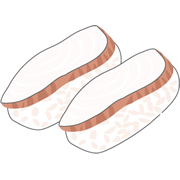 たい
43.4kcal
たい
43.4kcal
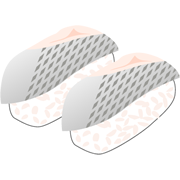 こはだ
51.9kcal
こはだ
51.9kcal
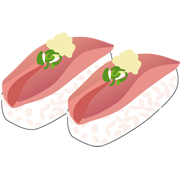 あじ
52.1kcal
あじ
52.1kcal
 60.4kcal
60.4kcal
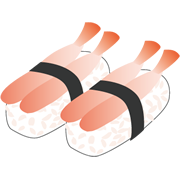 あまえび
35.8Kcal
あまえび
35.8Kcal
 えび
44.6kcal
えび
44.6kcal
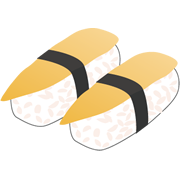 数の子
41.9kcal
数の子
41.9kcal
 うなぎ
78kcal
うなぎ
78kcal
 たまご
59.7Kcal
たまご
59.7Kcal
 いくら
52.9kcal
いくら
52.9kcal
 ねぎとろ
90kcal
ねぎとろ
90kcal
 うに
43.4kcal
うに
43.4kcal
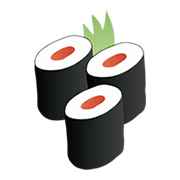 鉄火巻き1/4
24.4kcal
鉄火巻き1/4
24.4kcal
 かっぱ巻き1/4
17.2kcal
かっぱ巻き1/4
17.2kcal